この記事は、
勉強の目的とは抽象化する思考力を養うこと 1
の続きです。
この記事を知人に見せたところ、
抽象化する思考力って、何のことはない創造力のことでは?
と言われました。
その通りですね。「創造力」と言い換えてもいいかも知れません。「抽象化する思考力」とは、「洞察力」「観察力」「創造力」「理解力」「読解力」「判断力」などの総称として考えていました。正直、明確な定義はありません。
簡単に言ってしまえば、
ということです。

自分の頭で考えるということで、「創造力」をもとに記載します。
大工さんが家を建てるときに、2回建てる。
一回目は頭の中で建てて、二度目は実際に手を動かして建てる。
と言われるように、ものを造る際には、先ず、出来上がったものを頭の中で想像することから始まります。
いきなり設計図を書くことはない。ましてや、いきなり材料を切り出すこともない。先ずは、完成形をぼんやりながらでも、頭の中で想像してみる。この後の製作は、造る対象により異なります。詳細な設計図を書いてから造る場合もあれば、実際に造りながら考える場合もあります。
しかし、先ずは完成形を想像する。つまり、「想像力」があって創造ができる。ということです。
さて、子供たちの「想像力」を鍛えるためには、何が最も適しているかというと、賛否両論あると思いますし、大工さんの例からはかけ離れているようですが、私はやはり「読書」だと考えています。
ここに一冊の小説があったとします。この小説が、
①文章だけの小説
②挿絵が入った小説
③漫画になった小説
④アニメになった小説
となった場合、どれが一番取っ付き易いでしょうか?
「④→③→②→①」の順ですね。取っ付き易いということは楽なこと。楽なこととは、頭が楽をしているということ。つまり、場面を想像する必要が無いから、脳が働かないこと。
よく、話題になった小説が映画化されると、
あの役者では、小説のイメージに合わない。
そうなのです。このイメージすること、つまり、自分なりに「想像する」ことが何よりも大切なのです。
筋肉は、使わないと退化します。
脳も使わないと退化します。これは、自然の摂理です。
「想像力」を鍛えるためには、「読書」が最適だと書きました。小説を読むと、自分の頭で場面や登場人物を想像します。登場人物の心情や物語の時間的経過を考えます。評論でしたら、作者の意図していることを、文章から正確に読み取ろうとして考えます。技術書だって結局のところ、記載された内容を正確に理解するように考えます。

つまり、脳がフル活動します。
さて、「子供を読書好きにする」
これ、難しいですよね。小学校になってから、
うちの子は本を読まない。
と言われることがあります。
(最近は、親もスマホばかり見ているので、このようなことを言う親もなくなりましたが。)
「子供を読書好きにする」には、幼児期から絵本に親しませるのが最善です。幼児期の脳は発達段階にあります。「想像力」を身に着けている段階です。未だ、文字を認識することはできません。この時期に絵本を読み聞かせると、親に読み聞かせてもらった言葉をイメージして、絵本の絵に結び付けていきます。言葉からイメージして絵を見る。つまり「想像力」の基礎を鍛えています。
また、ページをめくるという手を使う行為、また、ページをめくって画面が変わるという行為自体に、心地よい感触を覚えていきます。そして何よりも、親に読み聞かせてもらった、親と一緒にいた、親に愛してもらっていた、と言う意識が潜在意識に残って、大人になって本を読むときにも、知らず知らずのうちに蘇るとも思えます。大人では、もちろん、「知識欲が満たされる」という側面が大きいですが。
そして、絵本の次に、「図鑑」のように、文章と絵が一緒に書(描)かれた書物に移っていきます。「図鑑」の文字を読んで、絵で確認して理解して行きます。記述している文章の内容は、全てが絵で表現されている訳ではないので、絵を参考にして、文章の意味を理解しようとします。こうして、「想像力」「理解力」「読解力」が養われて行きます。
最後には、文章だけで「想像力」「理解力」「読解力」を働かせて、記述されている内容を正確に理解するようになります。ちょうど、先ほどの「③→②→①」の順で、頭を使い脳を鍛えて、本の内容を理解するようになります。

幼児期に絵本に親しませなかったから、もう遅いか。
そんなことはありません。小学校になっても、中学校になっても、読書好きにすることはできます。
家族で読書する習慣をつけるだけで、子供が読書好きになる可能性があります。
これについては、別の機会に述べようと思います。
さて、学校の国語の授業では、教科書の文章を読んで生徒に要約させます。頭を使います。文章を読むだけでも頭を使うのに、それを短くまとめる。とても頭を使います。つまり、脳はフル活動します。脳を鍛えているのです。
また、英語の授業で、英語の文章を読んで日本語に訳します。全く未知の言語です。文法も違えば、表現している文字も違えば、単語も違う。それを解読して、適した日本語に訳す。頭を相当に使います。
日本語を英語に訳す英作文も、上と同じことを逆に行うので、これも頭を相当に使います。脳を鍛えています。
算数の授業ではどうでしょうか。算数では、分数、特に分数で割るというところ、また、少数で割るというところで、授業についていけなくなる子供がいます。ですが、それをすんなりこなしてしまう子供もいます。この差は何によるものなのでしょうか。
すんなりこなしてしまう子は、総じて計算問題も良くできる子です。つまり、数になじんでいる。数量感覚が身についている子です。このような子たちは、分数の割り算でも、少数の割り算でも、その仕組みは解らなくても何となく感覚で合点がいっています。脳が、数を使うという抽象的思考に慣れてきています。
また、計算問題が頭を使うことは、言を待たないでしょう。高齢者の認知症予防にも計算問題が取り入れられています。しかも、学校では計算問題を決められた時間内にやることになります。だた計算するだけでなく、早く正確にやります。そのための工夫が必要となります。また、「計算力」だけでなく「忍耐力」も必要になります。「忍耐力」は脳の前頭葉の成せるものです。ここでも、脳はフル回転します。ちなみに数量感覚が身についている子供でしたら、4桁の足し算でも、4桁の引き算でも、3桁どうしの掛け算でも、4桁割る3桁の割り算でも(これらは、今の学校ではやりません。やっても、とても短い授業時間です)、桁数が少ない計算方法から類推して、こなせるそうです。
昔から「読み」「書き」「そろばん」と言われています。「読解力」「表現力」「計算力」が重要と言うことです。先人は、経験から、「読解力」「表現力」「計算力」の重要性を認識していたのでしょう。
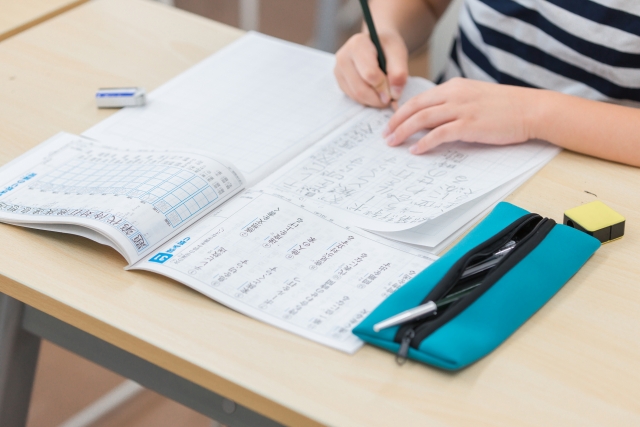
「脳の発達」「脳を鍛える」と言ってきました。何故、そこまで脳にこだわるのでしょうか?
人間は、25歳まで脳が成長し続けるそうです。そして一番最後に、「前頭葉」が発達します。「前頭葉」は人を人たらしめているもので、物事を理解したり、感情をコントロールしたり、他の人の気持ちを理解したりする部分です。高校生の頃は、感情に揺さぶられ物事に集中できなかった子が、25歳を過ぎたころから落ち着いてくるのも、この前頭葉の発達によるものです。逆に、前頭葉は一番早く老化します。高齢者が我慢ができなかったり、怒りっぽくなったり、自分勝手になるのは、この前頭葉の機能低下によるものです。
脳が発達し続けて25歳になるまでとは、子供たちにとってどのような時期なのでしょうか?
言うまでもなく、幼保・小・中・高・大の学童/学生の時期です。つまり、この学童/学生の時期が、脳の発達にとって、とても重要な時期となります。この時期に、脳を鍛える、「想像力」「洞察力」「観察力」「創造力」「理解力」「読解力」「判断力」などの考える力を身に着けることが、つまり、自分の頭で考える習慣を身に着けられるかどうかが、その後の人生を有意義に過ごせるかどうかを左右する、と言っても過言ではないと思います。
逆に、この時期に、脳を鍛えることを怠って25歳を過ぎてしまうと、それから、「想像力」「洞察力」「観察力」「創造力」「理解力」「読解力」「判断力」を身に着けることは、難しいかも知れません。
頭を使って考えないと、当たり前ですが脳は発達しません。脳は使わないと退化します。ここで、なるべく頭を使わない楽なことは何でしょうか。先ほどの「④」です。動画です。確かに動画は楽です。次から次へと映像が流れてきます。目で見ているだけで、何となく解った気がします。何も考える必要がありません。考える余裕すら与えてくれません。
最近は、電車の中でも、待合室でも、多くの人がスマートフォンを見ています。そして見ているコンテンツは、ほとんど動画です。動画は頭を使いませんので、暇つぶしには持って来いです。重ねて言いますが、脳は使わないと退化します。脳が退化すると、忘れっぽくなったり、怒りっぽくなったり、自分中心の考えを持ち自分勝手になります。さらには、認知症への耐性が下がります。何十年か後に、今の子供たちが社会を担っているときに、街中が認知症患者で溢れている、などということが杞憂で終わることを願っています。

「これからの授業は動画で行うべきだ。」と言う人がいます。果たしてそうなのでしょうか。確かに物理の「運動量保存の法則」とかは、動画の方が理解できるかも知れません。(ただし、宇宙空間の中で、摩擦を全く考慮しない動画でしたら。)パソコンの操作とか機械の操作とかは、動画の方が適しているでしょう。ですが、授業ではどうなのでしょう。「想像力」そして、それを基にした「創造力」は養われるのでしょうか。
ここで、最初の生徒の質問に戻ります。
生成AIがあれば、英語の勉強なんて要らないのでは?
生成AIがあれば、国語の授業なんて要らないのでは?
コンピューターがあれば、数学の授業なんて要らないのでは?
私はこう答えます。
確かに、これらの授業は、君の将来にも役に立たないかも知れない。
だけど、これらの授業を通して、君たちの考える力を養っている。
そしてそのことが、君たちの人生を豊かにする。
こういうと、今度は、
僕は、お笑い芸人になるのだから、そんなものは必要ない。
私は、ダンサーになるのだから、そんなものは必要ない。
(子供たちのなりたいものの上位にあるので、例として出しました。他意はありません。ご了承ください。)
というような答えが返ってきそうです。確かにそうかも知れません。
しかし、どんな職業にあっても、その道で生計を立てていくには、それ相応の努力が必要です。少しでも上手になるためには創意工夫が必要です。困難を乗り越えるための忍耐力も必要とされます。学童/学生の時期に、どんなにつまらないと感じる勉強でも、努力して工夫して自分の頭で考えてこなしていく。それが基礎となるはずです。できれば「達成感」が得られたり、「成功体験」が得られれば尚更いいでしょう。

そうして、
自分の頭で考える習慣と、基礎学力が身についていれば、どんな職業についても、豊かな人生を送ることができる。
と信じています。

コメント